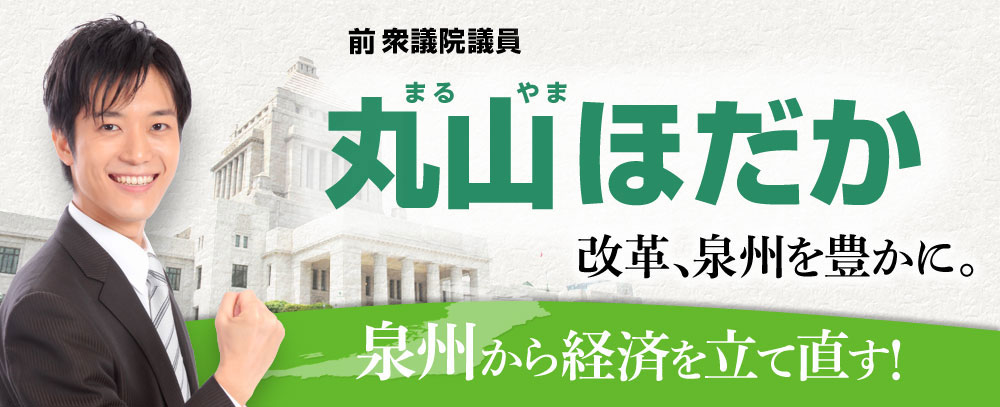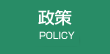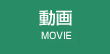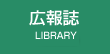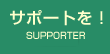2013年11月14日
こんばんは、丸山穂高です。
今週は経済産業委員会にて審議中の産業競争力法案について、
火曜日、水曜日と連続で質疑に立ちました。
質疑でも述べさせて頂いたように、
本法案では、同時に廃止となる産活法の改善反映ができているのかと、
規制緩和3層目の戦略特区でも実現できない大胆な規制緩和特例を
きちんとこの法案で認められるのかという実効性
の2点が胆となる部分だと考えています。
政府案では、約150条もの条文のうち、
実に3分の2にもあたる約100条が産活法の規定を引き継ぐものとなっております。
しかしながら、その元の産活法では、利用した企業が0件となる制度があるなど、
企業にとって使いづらいとの評も多い中、
これまでの産活法を総括し、問題点を大きく見直さなければ、
結局従来の支援策と変わりません。
また、これまでも似たような成長戦略を毎年のように出している中で、
規制を緩和する側の省庁の抵抗を抑えて、
企業がやってみたいという緩和特例を「実行」できるかどうかがカギとなります。
アベノミクスの3本目の矢、成長戦略や規制緩和については、
非常に疑問を感じるとともに、踏み込み不足を懸念しています。
国会ではその点、しっかりと具体的に確認してまいります。


今週は経済産業委員会にて審議中の産業競争力法案について、
火曜日、水曜日と連続で質疑に立ちました。
質疑でも述べさせて頂いたように、
本法案では、同時に廃止となる産活法の改善反映ができているのかと、
規制緩和3層目の戦略特区でも実現できない大胆な規制緩和特例を
きちんとこの法案で認められるのかという実効性
の2点が胆となる部分だと考えています。
政府案では、約150条もの条文のうち、
実に3分の2にもあたる約100条が産活法の規定を引き継ぐものとなっております。
しかしながら、その元の産活法では、利用した企業が0件となる制度があるなど、
企業にとって使いづらいとの評も多い中、
これまでの産活法を総括し、問題点を大きく見直さなければ、
結局従来の支援策と変わりません。
また、これまでも似たような成長戦略を毎年のように出している中で、
規制を緩和する側の省庁の抵抗を抑えて、
企業がやってみたいという緩和特例を「実行」できるかどうかがカギとなります。
アベノミクスの3本目の矢、成長戦略や規制緩和については、
非常に疑問を感じるとともに、踏み込み不足を懸念しています。
国会ではその点、しっかりと具体的に確認してまいります。